Menu
Menu



八千代エンジニヤリング【公式note】 |

海洋プラスチック問題への貢献度を
定量的に評価する
官公庁のお客様 |

AI交通量調査の時代が幕開け
AIを活用した交通量調査の省力化をサポート
企業のお客様 |

設備保全を見える化する
クラウド設備保全システム
企業のお客様 |

気候変動から自然資本まで
あらゆる環境課題に・・・・
企業のお客様 |

再生可能エネルギーで脱炭素経営。
企業のお客様 |

地域に新たな関係を再構築する。
企業のお客様 |
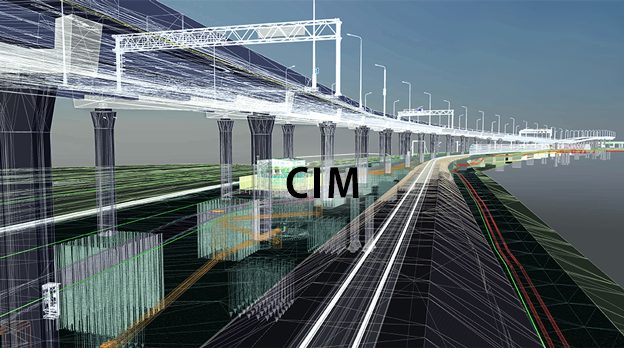
BIM/CIMを活用して、
労働生産性20%向上を実現させる。
官公庁のお客様 |
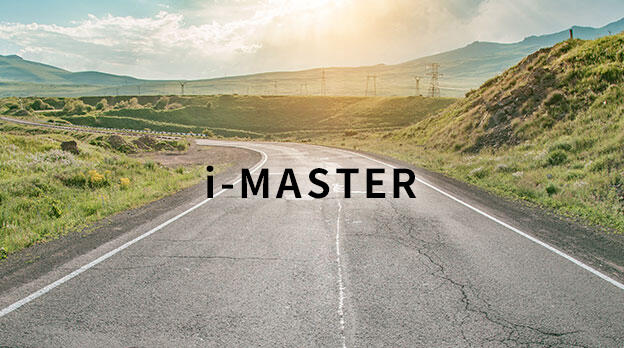
地域のインフラ管理、
まずは生産性30%アップ。
官公庁のお客様 |


私たちは、社会基盤から経済・産業、そして人々の生活といった社会と暮らしの課題を解決するコンサルタントです。※ 2023年7月時点のコンサルタント数を表示
152名
共創
さまざまな分野で共通して必要となる、社会マネジメント、環境計画、地質・地盤、機電の技術を集結し、全社的な技術連携の強化をリードします。
98名
都市デザイン
まちづくり、建築、環境施設など、都市を構成する各機能に関するサービスを提供しています。
273名
道路・鉄道
道路、鉄道、橋梁をはじめ交通事業に関する構想・計画から設計、施工、管理、維持管理・事業評価にいたるサービスを提供しています。
228名
河川・水工
河川・海岸、ダム、砂防、港湾・海洋の4分野で、国内外において総合力を発揮するサービスを提供しています。
134名
海外
多岐にわたるサービスを約150カ国で提供しています。
112名
研究・事業開発
社会問題を解決する新たな技術の研究や、研究成果を実装して社会へ価値を提供する事業開発を進めています。